「自己愛性パーソナリティ障害には、具体的にどんな特徴があるの?」
「自己愛性パーソナリティ障害の人は、どんな考えや思考回路をしているの?」
「究極のナルシスト」「笑えないナルシスト」などともいわれる自己愛性パーソナリティ障害(NPD)※。どこか無理している感や妙に演出されたような雰囲気など、自然体や飾らない人柄とはほど遠い態度・様子に違和感を覚えたことがある人もいるのではないでしょうか。
※「Narcissistic Personality Disorder」の略
単純なかっこつけでは済まず、急にキレはじめたり、矛盾した言動をくり返したりする姿に、どんな考えや価値観を持っているのかと気になっている人も少なくないはず。自己愛性パーソナリティ障害を扱った本を読むと、その背景にある心理やメカニズムなどを理解するヒントが得られるでしょう。
そこで本記事では実際に読んだ本の中から、自己愛性パーソナリティ障害(NPD)について学べる人気おすすめ本をランキング形式で紹介していきます。本記事を読めば、どの本が分かりやすくておすすめか、それぞれの本にはどんな内容が書かれているのかなどが分かるので、ぜひ参考にしてみてください。
自己愛性パーソナリティ障害(NPD)について学べる人気おすすめ本
- 【1位】『結局、自分のことしか考えない人たち』サンディ・ホチキス
- 【2位】『なぜ、あの人は自分のことしか考えられないのか』加藤諦三
- 【3位】『自己愛性パーソナリティ障害 正しい理解と治療法』市橋秀夫
【1位】『結局、自分のことしか考えない人たち』サンディ・ホチキス

概要・あらすじ
家族や友人、上司、同僚など、意外と身近に潜む「自己愛人間」。特徴は「傲慢な態度で見下す」「ねたみの対象をこきおろす」「特別扱いを求める」「相手を自分の一部とみなす」など。自己愛人間の複雑な心理構造を解き明かし、その毒から身を守るための戦略を解説した一冊。
感想・おすすめポイント
- 回避された恥
- 自分と他者の区別がつかない
- 境界を設定する
本書は、自己愛の強い傲慢な人間(=自己愛人間)の心理や対処法などを解説した一冊。本書によると、自己愛人間の7つの大罪(特徴)は以下の通りです。
- 恥を知らない
- 歪曲して、幻想を作り出す
- 傲慢な態度で見下す
- ねたみの対象をこき下ろす
- 特別扱いを求める
- 他者を平気で利用する
- 相手を自分の一部とみなす
特に恥を健全に処理できない点が印象的で、不健全な自己愛の奥には恥への強い意識が潜んでいる。親が子どもに与えた恥をうまく和らげないと、子どもは恥の意識を処理する独自の方法を発達させる。要するに恥という耐えがたい感情を遠ざけるために、自分は特別だという幻想にしがみつくとのこと。
心理学者が「回避された恥」と呼ぶ方法で、適切に処理されなかった恥は否認や冷淡さ、非難、怒りの形で表に現れる。時には「僕の責任ではない」などといった言葉のように、責任転嫁のような態度になるそうです。
また、自分と他者の区別がつかないのも特徴。他者は自分の要求を満たすための存在で、自分の要求を満たさないなら存在価値すら否定されるとのこと。
原因は幼少期の体験で、幼少期の子どもは母親との心理的な境界がなく、「二人は一体」という錯覚の中で万能感を得ながら生きている。しかし成長とともに自分は無力で、本当に力があるのは母親側だと気づく。そのとき、一部の子どもは錯覚の中にとどまり続け、相手を自分の延長として扱うようになるようです。
自己愛人間への対策の一つは境界を設定することで、自己愛人間は日常的に境界線を侵害する。具体的には自分宛ての手紙を許可なく読む、勝手にデスクの中を調べるなど。そのため自分のほうで境界線を設定し、何が何でも守り抜くことが大切だと強調しています。
本書は全体を通してロジックが明確で分かりやすく、人間の心理に詳しくなくとも興味深く読み進められます。本書を読むと、自己愛人間は自分とはかけ離れた異常な存在ではなく、「ああ、こういう時期が自分にもあったかも…」と幼少期なども含めて感じるかもしれません。
また具体的な戦略(対策)まで丁寧に書かれているため、人間関係に役立つ実用的な本ともいえるでしょう。自己愛人間との関わりに心が消耗している人にとっては、自分を守るための具体的なヒントが得られるかもしれません。
ちなみに本書には他にも青春期のちなみに本書には他にも青春期の自己愛人間や恋に落ちた自己愛人間、職場の自己愛人間などの事例に加え、子どもを自己愛人間にしないための考えなども紹介されています。
基本情報
| 著者 | サンディ・ホチキス |
| タイトル | 結局、自分のことしか考えない人たち:自己愛人間への対応術 |
| 出版社 | 草思社 |
| 発売日 | 2020/2/6 |
| ページ数 | 186ページ |
| おすすめ度 | ★★★★☆(SSランク) |
| 楽天 | https://a.r10.to/hFpI63 |
| Amazon | https://amzn.to/42BDUtM |
【2位】『なぜ、あの人は自分のことしか考えられないのか』加藤諦三
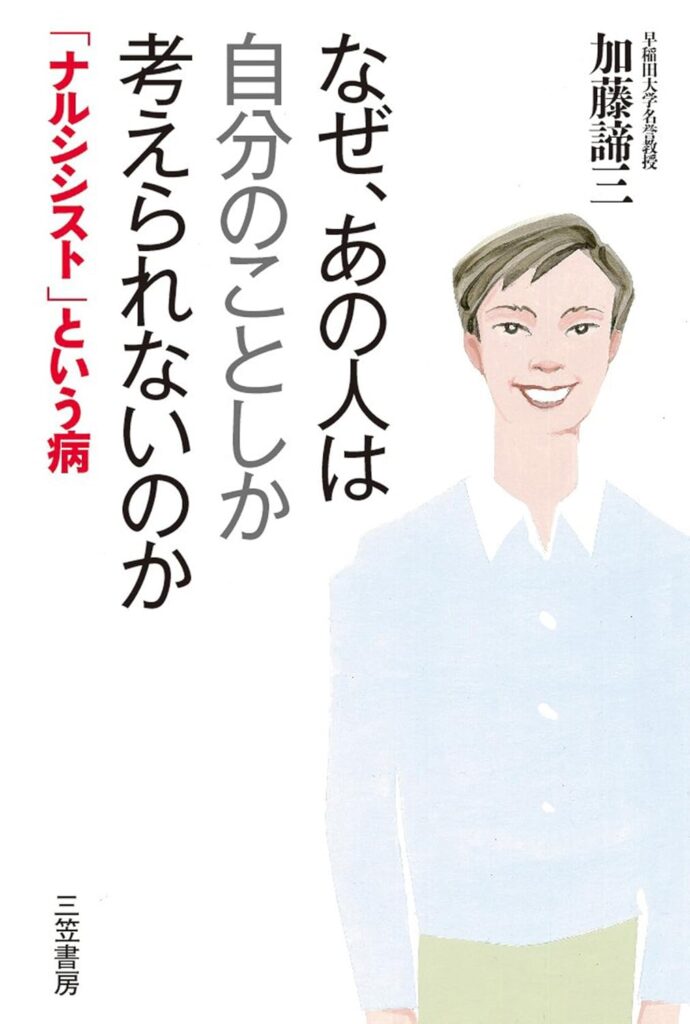
概要・あらすじ
一見いい人なのに、自分にしか興味がない、わがまま、不幸自慢、人の話を聞けない。それらはすべてナルシシストの症状。ナルシシストであればあるほど、現実に傷つきやすくなる。ナルシシズムから解放されれば、人を憎んだり、責めたり、恨んだりしないで、いつも生きていける。人の言動に過敏に反応して苦しむこともない。ナルシシストの心理などを解説した一冊。
感想・おすすめポイント
- 心の底にあるのは「孤独&恐怖」
- ナルシシズムは「賞賛依存症」
- 解消方法は「好きなことを見つける」
本書は、ナルシシストの心理やナルシシズムの解消方法などを解説した一冊。そもそもナルシシストとは人が自分をどう見ているかを気にする目立ちたがり屋で、いつも誰も私の苦しみを分かってくれないと苦しんでいる。天国のように見える環境にいても不幸である、とのこと。
心の底にあるのは孤独と恐怖で、いつもビクビクして平常な気持ちを維持するのに精一杯。たとえ意識の上では高い自己評価でも、無意識では逆に空虚感に悩み、自己蔑視している。とにかく劣等感が深刻で、本当の自分がバレないかとビクビクしている。表面上は自己陶酔しながらも、その心の本質は劣等感だと指摘しています。
自分自身であろうとすること、別の言い方をすれば、幸せになることの最大の障害はナルシシズムで、ナルシシズムとは賞賛依存症。ナルシシストにとって、自己の存在証明は他者の賞賛。したがって批判されることは自己の存在証明を否定されることで、その怒りと落ち込みは常人には想像を絶するものがあるといいます。
人間は生まれて以来、成長欲求と退行欲求の葛藤の中で生きている。成長欲求が勝った者は幸せになり、退行欲求が勝った者は不幸になる。ナルシシズムは成長の敵、つまり幸せの敵とまで述べられています。
ナルシシズムを解消する方法は意外と単純で、「苦しい!」と訴えるよりも、自分のナルシシズムに気がつき、他者のことを考える。ナルシシストは好きなものがない、好きな人がいないのも重要な特徴で、自己陶酔しているから対象(他者)への関心がないとのこと。
とにかく何でもいいから好きなことを見つけ、自己賞賛のためではなく、自分が興味あることにエネルギーを注ぐことが大切。まずは自分は自己執着が強いから対象への関心がないと認め、次に賞賛がなくても楽しく生きている人を観察して見習うといいと述べられています。
全体的に辛らつな語り口ながらも、ナルシシズムの問題が想像以上に重く根深いことを痛感します。虐待や離婚、事件、戦争などの背景にもナルシシズムが関係している可能性があり、人間関係や社会に与える影響は少なくないと感じられます。また単にナルシシズムの特徴を述べるだけでなく、原因や解消方法なども紹介されているのも嬉しいポイントですね。
なお、本書には他にも2種類のナルシシストに共通することや、ナルシシストと感情の激しい人の違い、ナルシシスト度を測る8つのチェックリスト、ナルシシズムと被害者意識&悲観主義の関係などが紹介されています。
基本情報
| 著者 | 加藤諦三(かとうたいぞう) |
| タイトル | なぜ、あの人は自分のことしか考えられないのか――「ナルシシスト」という病 |
| 出版社 | 三笠書房 |
| 発売日 | 2016/9/7 |
| ページ数 | 204ページ |
| ジャンル | ノンフィクション |
| 受賞・候補歴 | – |
| メディアミックス | – |
| おすすめ度 | ★★★★☆(SSランク) |
| 楽天 | https://a.r10.to/hReklQ |
| Amazon | https://amzn.to/4qdVtKR |
【3位】『自己愛性パーソナリティ障害 正しい理解と治療法』市橋秀夫
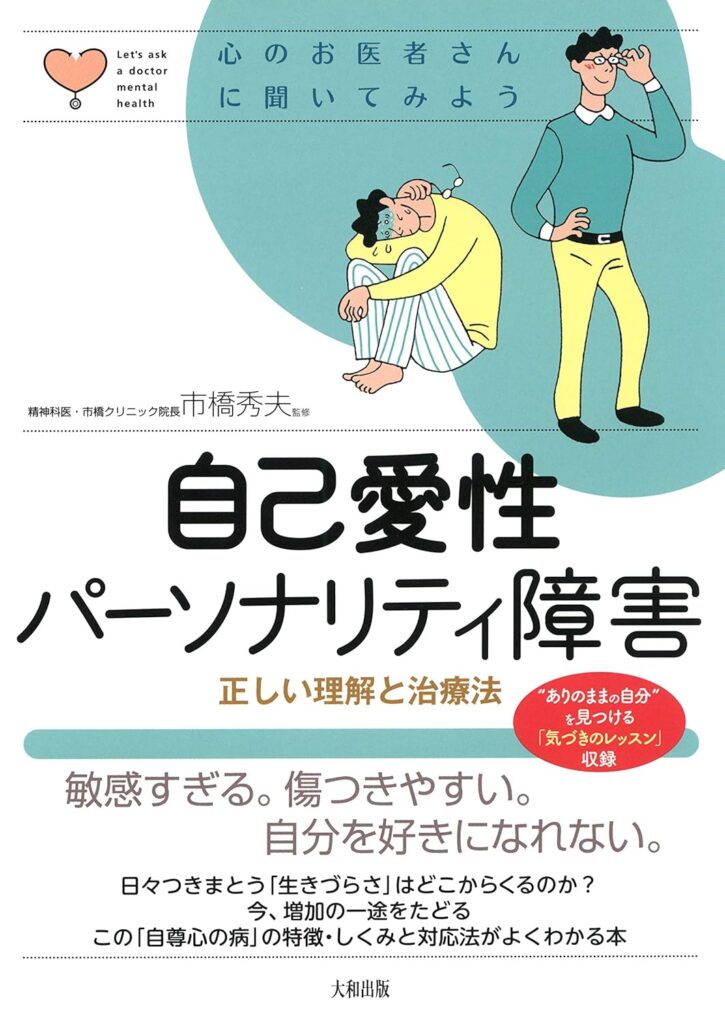
概要・あらすじ
「敏感すぎる」「傷つきやすい」「自分を好きになれない」といった特徴を持つ自己愛性パーソナリティ障害。肥大化した自尊心に振り回される病で、うつ病やDV、引きこもり・不登校などの現象を引き起こしやすい。周囲に限らず、本人も自らの障害の問題点に気づける一冊。
感想・おすすめポイント
- 引き起こしがちな7つの現象
- 周囲の印象とは異なる特性を持つ
- 周囲が対応する際に守るべき8つのポイント
本書は自己愛性パーソナリティ障害の特性や考え方、行動パターン、思考パターンなどを解説した一冊です。自己愛性パーソナリティ障害は肥大化した自尊心に振り回される病で、実生活の中でさまざまなトラブルを引き起こします。
特に引き起こしがちな現象は以下の通りで、こうした現象の裏に自尊心の問題があることに、本人や周囲だけでなく医師さえも気づきにくいそうです。根本原因を取り除けないため、頻繫にトラブルをくり返してしまいます。
- 摂食障害
- 非定型うつ※
- 引きこもり・不登校
- 強迫性障害(不潔恐怖や醜形恐怖など)
- DV(ドメスティック・バイオレンス)
- ストーカー
- クレーマー
※従来のうつ病とは異なる症状が出るタイプ。気分の反応性や拒絶過敏性、過食、過眠などの特徴を持つ
※参考:品川メンタルクリニック
また自己愛性パーソナリティー障害と聞くと、「自分大好き」「うぬぼれが強い」と思われがちですが、実際には以下の特性を持っていると指摘しています。
- 自分のことが好きになれない
- 他人を信用できない
- 人間関係は常に勝ち負けになる
- 自分が自分以上でないといけないという強迫観念を持っている
- 他人の成功に対して、嫉妬と羨望の感情が収まらない
- 自分が特別な存在であることをさりげなく、あるいはあからさまに示したがる
- うまくいっているときには頑張れるが、思い通りにいかなくなると努力を続けられなくなる
- 挫折に弱く、立ち直ることが困難
- 批判されたり叱責されたりすることが極度に苦手
- 自分がどう見られているかばかり気にする
- 自分が賞賛されているイメージに耽溺する
特に人間関係のパターンが印象的で、他人とは対等な関係になりにくく競争相手になってしまう。人との関係は基本的に「見下すか」「見下されるか」の2択で、家族だけは唯一自分の延長線上に捉えることが多いようです。ちなみに本書には自己愛性パーソナリティー障害の対人意識が分かる、ある政治家の言葉も紹介されています。
自己愛性パーソナリティー障害の人との付き合いは難しいですが、以下の8つのポイントを念頭において対応することが大切であるようです。
- 気持ちを分かってあげる
- 目線を本人と同じ高さに
- 言い訳をしない
- 分かろうとする態度を示す
- お役人的な態度、硬直的な態度を取らない
- 支配的な態度、威圧的な態度を取らない
- こちらが間違ったときにはきちんと謝罪する
- 規則優先な対応は避けるが、原則は譲らない
全体を通して、自己愛性パーソナリティー障害の人に抱いていたイメージとは異なる姿を感じられるのが新鮮です。どれだけ自分が好きなのかと思っている人は、本書を読むと見方が変わるかもしれません。また全体的にイラストが多く使われているため、文章が苦手でも理解しやすいのも嬉しいポイントです。
なお、本書には他にも自己愛性パーソナリティー障害の原因や背景に加え、病理の構造や特有の考え方、気づきのレッスン、対人関係でやりがちなことなどが紹介されています。
基本情報
| 著者 | 市橋秀夫(いちはしひでお) |
| タイトル | 心のお医者さんに聞いてみよう 自己愛性パーソナリティ障害 正しい理解と治療法 |
| 出版社 | PHP研究所 |
| 発売日 | 2018/8/7 |
| ページ数 | 99ページ |
| おすすめ度 | ★★★☆☆(Sランク) |
| 楽天 | https://a.r10.to/hg8rFA |
| Amazon | https://amzn.to/46FeOeT |
関連記事
まとめ
自己愛性パーソナリティ障害は「究極のナルシスト」などともいわれ、自然体とは無縁の態度や矛盾した言動に周囲を戸惑わせることが少なくありません。
ただ、自己愛性パーソナリティ障害の特徴や心理を知ると、単純に「自分大好き」というイメージでは片づけられないことが分かります。
また自己愛性パーソナリティ障害の人との関わり方だけでなく、自分の心の中にある似たような傾向を見つめ直すきっかけにもなり、自己理解を深める手助けともなってくれるでしょう。

